 <唐門>
<唐門>
この真っ白の色は貝殻をすりつぶして作られた胡粉(ごふん)で塗られています。
 梅のようですが、昇龍と降龍でしょうか。
梅のようですが、昇龍と降龍でしょうか。
素敵ですね~。
 かつては、将軍に謁見できる身分の者のみ門をくぐれたそうです。
かつては、将軍に謁見できる身分の者のみ門をくぐれたそうです。
通常営業時は閉ざされていますが、年末新年や例大祭などの時期にのみ開放。そんなこととは知らずラッキーでした。
 門全体には彫刻が600以上。
門全体には彫刻が600以上。
中国古代史に登場する「許由と巣父(きょゆうとそうほ)」なども見られます。
ストーリがあり面白いですね。
許由(きょゆう)
許由は陽城槐里の出身。堯帝が天下を譲ろうとした際、その申し出を拒否し、自らの耳が汚れたとして頴水で耳を洗い、箕山に隠棲。この行動は世俗の権力や地位を嫌い、清廉な生活を重んじる姿勢を象徴。許由は身に蓄えをほとんど持たず、水も手で掬って飲む質素な生活を送っていたと伝えられている。
巣父(そうほ)
巣父は山中に住み、樹上に家を作って寝る隠者。許由が川で耳を洗うのを見た巣父は、「汚れた水を牛に飲ませるわけにはいかない」と考え、牛を連れて上流に行った。
この行動は他者への配慮や高潔な倫理観を示すものとして語り継がれている。
 本殿へ進む回廊へ向かいます。
本殿へ進む回廊へ向かいます。
本殿は撮影禁止の為写真はありませんが、天井に沢山の龍の絵がありました。
この中で陽明門の天井と同じ龍の絵があるそうで探してみましたが、思ったものと外れてたみたいな・・・・💦
こちらを出て右手へ。ここでまたちょっと家康の話に。
<なぜ家康のお墓は日光に?>
晩年を駿府(静岡市葵区)で大御所として過ごした家康は遺言を残します。
その遺言では「遺体は駿河国の久能山に葬り、江戸の増上寺で葬儀を行い、三河国の大樹寺に位牌を納め、一周忌が過ぎて後、下野の日光山に小堂を建てて勧請せよ、八州の鎮守になろう」と残しています。
なぜ行ったこともない日光へ自分の遺体を移すのか?これは疑問になるところ。
それには二人の僧がアドバイスしていたと考えられます。
<家康をバックアップした二人の僧>
・以心崇伝
・南光坊天海
風水や陰陽道の要素を取り入れ、江戸城の真北をアドバイス。
北には北極星があるからです。北極星は動かないのえ「不動の星」と呼ばれる為、江戸城を守護し日本の平和を守る為に久能山から一年後に遺体を移し、家康自身が神となって守護する為に祀るよう指示したのです。
慎重な家康が、徳川・江戸・日本というように視野を広げ、自身が守り神となっていつまでも平和で安泰な国を願ったのは、あの数々の彫刻や装飾を見ても本当にそうなんだろうな~感じ取れました。
 <亀石>
<亀石>
ちょうど分岐の所で亀さんがいました!
周りの人から「誰かが石を置いたのかな」と言って誰も近づく人はいなかったけど、手を近くに当てるとこの亀の頭の左側がビリビリ感が凄かったですよ。
小さい石は誰かが置いたようにも見えますが、亀を作ったのはちゃんと意味があります。
<霊獣の亀>
この中央の石の下はノボリが立てられるよう穴が開いています。ただこれはノボリだけの意味ではなく、この石は亀=霊獣としての役割があります。
家康が北に位置する北極星は動かぬ星として自身が神となってこの地から日本を守ると言った、その北極星に注目。
<北極星とは>
妙見菩薩(みょうけんぼさつ)
天之御中主神(アメノミナカヌシノカミ)
北極星や北斗七星を神格化した存在とされています。
そしてその神々を守る霊獣に「亀」がいるんですね。
この亀に気付く人は少ないと思います。
でも手を当ててみると、本当に温かいエネルギーを感じるので、行かれた人は是非やってみてください。また、亀さんにお礼を言うといいでしょう。
この亀さんの右の道を真っすぐ行くと鳴き龍の場所になります。 相変わらず装飾が凄い。
相変わらず装飾が凄い。
 <輪王寺薬師堂>
<輪王寺薬師堂>
日光東照宮内にありますが、ここは輪王寺薬師堂になります。
<鳴き龍:撮影禁止>
狩野永真安信の墨で描かれた龍の絵。
こちらは凹凸を利用して、龍の頭の真下で拍子木を打つと鳴きますが、実は真下でなくても特定の柱で叩いても鳴きます。
鈴の音のような優しい響きでコロコロと聞こえて可愛いです。
本当に顔のあたりから聞こえてくるんですよね。面白いですね~。
こちらを出て先ほどの亀の所まで来たら、亀の手足となる石がぐちゃぐちゃになっていたので、また元に戻しました。
次回は二荒山神社


 2月13日(金)先勝・一粒万倍日・大明日・神吉日
2月13日(金)先勝・一粒万倍日・大明日・神吉日 この先は奥宮へ繋がっています。
この先は奥宮へ繋がっています。 スフィンクスっぽい獅子ですね。
スフィンクスっぽい獅子ですね。 金ぴか~。
金ぴか~。 長い道のりの石廊下。こちらを進み、
長い道のりの石廊下。こちらを進み、
 ぼかしている所が多くてスミマセン。
ぼかしている所が多くてスミマセン。 結界が張られていて静かで荘厳な雰囲気。
結界が張られていて静かで荘厳な雰囲気。 重厚感のあるお墓。
重厚感のあるお墓。 お墓の周りを一周。りっぱなお墓です。
お墓の周りを一周。りっぱなお墓です。
 御祈祷場まで戻って来ました。
御祈祷場まで戻って来ました。


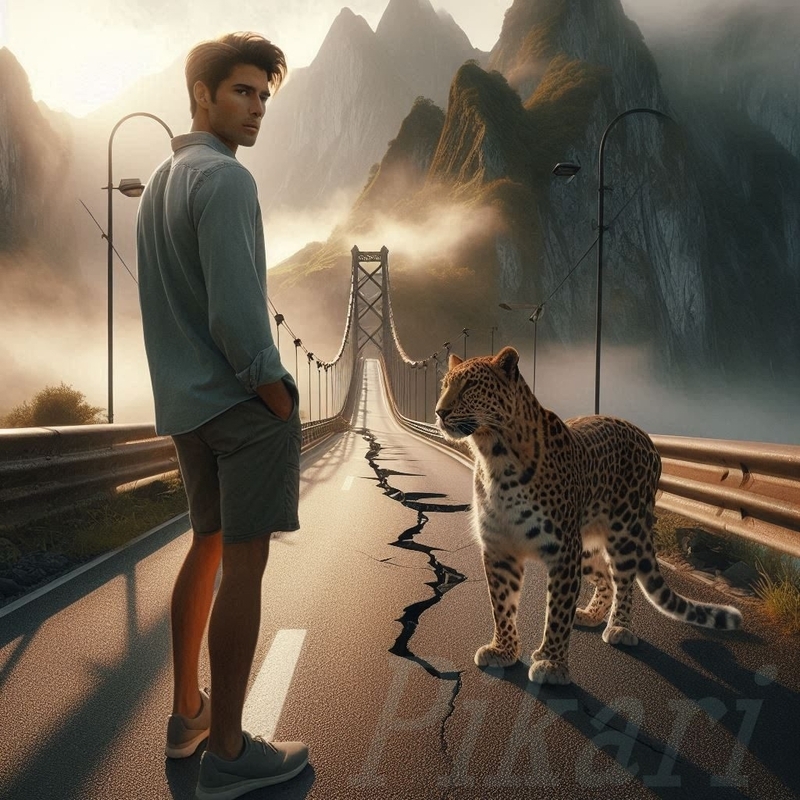 2月9日(月)先負・不成就日・寅の日
2月9日(月)先負・不成就日・寅の日 2月8日(日)友引・一粒万倍日・天恩日
2月8日(日)友引・一粒万倍日・天恩日